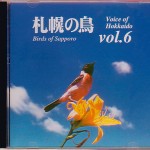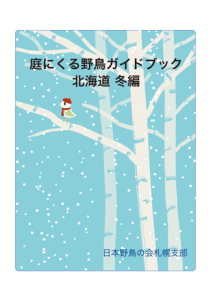カマキリがおしえてくれたこと
断続的に激しい雨が降るような日々が続き収穫しそこなっていた大豆を、今度は雪が降る前にと、数日の晴れ間を狙って一気に刈りとっていたときでした。これを、みつけたのは。
私は関東で存分に外遊びをして育ったので、これはもうみるからにおなじみの、たくさん楽しませてもらってきたあの虫のタマゴなのですが、にわかに断定しきれず、お仲間の詳しいみなさまに連絡して確認しました。少々、興奮気味に。
道南が生息の北限だったはずのカマキリは特に今年、道内のさまざまな地域で多く目撃されているという情報を知っていました。しかしみつかったのはタマゴです。しかも我が家の畑の大豆にくっついていたのです。瞬時に想いはかけめぐり、眠れなくなるぐらいになっていました。成虫を観察できなかった悔しさがまずひと段落すると、成長段階のいつ頃からこの畑で過ごしていたのか、何を食べていたのか(食べて“くれて”いたのか)、産卵はいつ頃だったのか、卵は雪の下でも丈夫に越冬できるのか・・・。北海道のカマキリへのぼんやりとした興味が、がぜん詳細に、とどまることなくわきあがってきました。
興味を持ってひとつの生物を観るということは、形態などそのものを観るだけにとどまらず、その餌となるもの、それを捕食するもの、周囲の環境、生態系のバランスなど、徐々に視点が拡がっていく可能性をはらんでいます。自分が観察したことと周知の来歴を照らしあわせてみることで、現在の自然環境の在り方にまで想いがおよぶこともあるでしょう。

カマキリの卵嚢
まだ選別の途中なのですが、収穫した大豆の状態は概ね良好で、歩留まりも高いようです。タマゴがついていたのは、大豆を栽培していた一帯のほぼ中心の位置でした。カマキリが大いに捕食に励んでくれていたのは、もしかしたらカメムシかもしれません。どうでしょうか。
畑はけっこう広いのですが、私は農家ではなく、その年の状況に任せるように気楽な栽培をしています。雑草の移り変わりや、畑にくる生物たちの姿は、おおらかにゆったり見守ることがほとんどなので、また来シーズンどうなるのかたのしみです。なんだか・・・畑とのつきあいも、自然界への興味関心も、与えられた環境や仲間へのありがたさも、より豊かに感じられているではないですか。
カマキリさん、どうもありがとう。